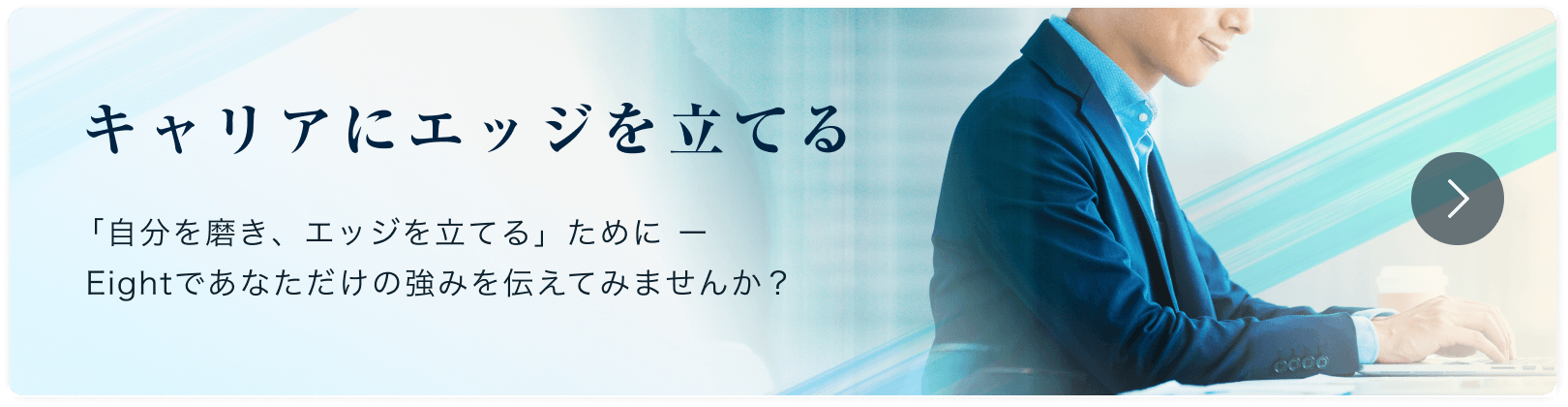フォーチュン誌が企業文化に関する評価を元に発表している「最も働きがいのある企業100社」に、3年連続で選出されたヴイエムウェア株式会社。本社をアメリカに持つ外資系企業だが、その根底にあるカルチャーには、よくある外資系企業のイメージとは少し違う「働きやすさ」があるようだ。
読者の皆さんは、外資系企業と聞いてどんな環境をイメージするだろう。多くは、「個人プレーで成果第一主義」「ドライな人間関係」「社内の共通言語は英語」「外国人の社長」などといったところだろうか。
そのイメージは間違っていないし、それが外資系企業で働く上での魅力でもあるのだろう。
今回取材した企業もまた、アメリカに本社を持ち、社員数は全世界で3万5000人を超える外資系企業である。サーバー仮想化の技術における第一人者であり、あらゆるITリソースのソフトウェアによる仮想化と、マルチクラウドを牽引するヴイエムウェア株式会社(以下、ヴイエムウェア)だ。同社は、フォーチュン誌が、企業文化に関する評価を元に発表している「最も働きがいのある企業100社」に、3年連続で選出された実績を持つ。
中をのぞくと、さまざまな背景を持った社員がいたり、場所を選ばない働き方が当たり前だったりしていて、その辺りは外資系企業らしさを感じる。
一方、よくあるそれのイメージとは少し違う雰囲気もある。例えば、チームプレーをとても大事にしていたり、個人間のコミュニケーションを密に取っていたり、社員をきめ細かなケアでサポートしたり。「働きやすさ」につながる要素がいろいろと目に留まる。どうやら、外資系の良い面はそのままに、外資系っぽくないカルチャーも加わったユニークな環境があるようだ。
ソリューションビジネスグループ統括・ネットワーク&セキュリティ事業部長・小林泰子は、まさにその、「働きやすい」環境をつくる活動「ダイバーシティ&インクルージョン」を推進している人物の一人だ。自身もまた、3年ほど前から長野県・軽井沢に移住し、リモートワークとオフィス出社をバランスよく織り交ぜ、自由な働き方を体現している(2020年8月取材時はフルリモートワーク)。
30年以上、外資系IT企業で勤務をしてきたという小林はいま、ヴイエムウェアの「働き方」をどう感じているのだろうか。また同社のこの「外資系っぽくないカルチャー」は、どのようにして形成されているのか。その答えが知りたくて、軽井沢にある小林の自宅を訪ねた。

性別、国籍、キャリア…みんな背景が違うから面白い
━━小林さんはIT業界の複数の外資系企業を経験されているとうかがいました。ヴイエムウェアに入社された当初、どんな印象を受けましたか?
長い間IT業界で働いてきた中で、ヴイエムウェアは製品としてのシェアを持っているすごく大きな会社という印象がありました。でも、実際に中に入ると、スタートアップの延長線上にあるというか、良い意味で「どんな風にでも変わっていける会社」という感じなんです。米国本社に対して「こうしたい」と思うことをどんどん提案できる環境もあって。だから一人ひとりが試行錯誤しながらすごく自由に働いています。私が感じた、前職以前との最も大きなギャップはその部分です。
━━組織はどんな構成なのでしょう。
当社は仮想化の技術を軸にソフトウェア製品やクラウドサービスのポートフォリオを広げている会社なので、組織は大きく分けると、営業、SE、保守サポート、そして当社のソフトウェア・サービスを最適にご利用いただくためのプロフェッショナルサービスという職種を中心に、人事やマーケティングなどのサポートファンクションも整っています。
他の外資系企業と少し異なるのは、顧客をサポートする職種の比重がとても大きいことです。それは日本のお客様のメンタリティに合わせたサポートを行うためです。日本のお客様は、製品をよりしっかり理解することを望まれますし、当社が扱う仮想化ソフトウェアはシステムの基幹となる部分ですから、確実な安定性も求められます。そういう意味で、サポートにはかなり投資をしています。

━━社員の皆さまはどんな方ですか? 外国籍の社員も多いと聞きました。
はい、一言で言うと「ダイバーシティな組織」という表現になってしまいますが、本当にいろんな人がいます。外国籍の社員も在籍しています。社長のジョン・ロバートソンもカナダ人です。外資系企業では、本社から外国人社長が派遣されてくることはよくありますが、ジョンはそうではありません。学生時代に日本に来て、以来ずっと日本に住んで働いている「日本のサラリーマンのおじさん」みたいな感じ(笑)。見た目は外国人ですが日本語がペラペラ、日本人の心がわかる人です。それでいて、仕事が終われば早く帰るし、土・日は絶対に働かないし、すごく家族思い。日本人の良さと外国人の良さを両方持ち合わせている。彼の独特な雰囲気が、この会社のカルチャーを特徴的なものにしていると思います。
━━なるほど、外資系だけど日本企業っぽくもあると。女性社員も増えているとか。
はい、女性の社員もどんどん増えていて、出産後に復職する人も出てきました。全体的に30代・40代のメンバーが中心なので共働きで子育て中の人が多く、子育てに積極的なイクメンもたくさんいるので、働く女性への理解もあります。子供の送り迎えなども含めて、それぞれのプライベートの予定を尊重するのが当たり前のカルチャーです。
私がヴイエムウェアに入社して強く感じたのは、「今まで働いてきた会社は、全然ダイバーシティじゃなかった」ということでした。以前働いていた会社も、確かに女性社員は多く、女性マネージャーもいて、外国籍の社員も多く働いていた。でも、皆が一つの決まったカルチャーの中でずっと働いているので、常識だと思っていることが皆同じなんです。
━━ヴイエムウェアは違う?
はい、ヴイエムウェアは中途入社が9割以上で、いろんなバックグラウンドの人が集まっているため、それぞれ、仕事との向き合い方のベースが全く違います。それはある意味、すごく面倒くさい。でも、裏を返せば「新鮮な学び」がたくさんあるということでもあります。「確かにそういう考え方もあるなあ」と気づかされることが多いのです。
よく「ダイバーシティがビジネスに貢献する」といいますが、当社は体裁だけでなく、リアルにそう思える環境が整っています。新しいやり方が常に採用されるんです。社員数だけで言えば男性が多いですが、だからといってダイバーシティが進んでいないとは全く思いません。だって「こんなにいっぱい、いろんな人がいるじゃん」って(笑)。女性も働きやすいですし、活躍している人もたくさんいますよ。

「みんなで考える」が当たり前の強固なチームワーク
━━なぜ多様性が成り立つのでしょう?
当社には「VMinclusion」という大きなイニシアチブがあるからだと思います。お互いを尊重し、認め合うインクルーシブなカルチャーを作ろうというメッセージが、日常的に会社の中で発信され続けているので、自然とその感覚が染み付いているのでしょう。

また、頻繁に1対1で会話をするミーティングをやっています。それもあえて違うチームの人と。困っていることや悩んでいることを話しながら、必要があれば相手の意見を補正しながらお互いを理解し合う。ここでもやはり、「こういう考え方もあるのか」と気づくことが多いですね。
それから、「PechaKucha(ぺちゃくちゃ)」という、四半期ごとのプレゼンテーションイベントもあります。「仕事以外」の20枚の写真を、一枚20秒でプレゼンする場で、そこでも「実はこんな人だったんだな」という気づきが生まれる。普段はなかなか関わることのない人のことを知る良い機会ですし、チームを越えた横のつながりも強くなるので、その後の仕事もやりやすくなるんですよね。


━━仕事以外のコミュニケーションも多そうですね。
そうですね。いろんな人と知り合う場があって、そこでお互いを認め合っていくことを常に醸成しているのだと思います。
社内ではよく「どう思う?」という言葉を耳にします。「相手の意見をまず聞く」というカルチャーがあり、基本的には「皆で考える」ことを大事にしていて。皆で「どうする?」と話しながら、立場を気にせず、年齢差があっても割と遠慮もせずに、自由に発言できる環境です。
━━外資系企業は個人プレーヤー集団というイメージがありますが、ヴイエムウェアはなんだか少し違いますね。
もちろん、個人の成果は常に求められていますから、そういう部分がないわけではありません。ただ、お客様あっての日本法人であり、提案活動にしろ、トラブルにしろ、誰か一人の責任というよりも「みんなで何とかしよう」という気持ちが一際強い会社だと思います。「これは自分の仕事の範囲ではないから知らない」という人はいません。一人ひとりが自分の強みを活かして、意見しながら解決策を探します。
だから成功した時も褒め合うんですよ。「この案件、おかげさまでクローズできました!」みたいなメールが回ってくると、皆も「すごいね!」などとどんどん返信します。良い取り組みがあった時は、違う部署の人が「今度やり方を教えて!」と“全員に返信”で返す。
こうした社風は前職の会社と大きく異なるため、正直なところ最初は少し抵抗がありました。でも、メッセージを送る側としては、サポートしてもらった人に感謝をきちんと伝え、皆と分かち合いたいという思いがあり、返す側も、それを一緒に喜びたいという思いがある。それを素直に表現しているんです。ですから今は、すごく良い習慣だと思っています。
例えば私のような営業部の場合は、やっぱり製品の売り上げをどうやって上げるかが一番大切です。そのためにいろんな施策に取り組み、いかに成功させるかを常に考えています。だからこそ、担当した仕事に対して社内からフィードバックがあり、他のチームともつながって、会社に貢献できたときは、やりがいを感じますね。

━━ 個人どころか、チームを越えた一体感がありますね。
そうですね。チームジャパンの精神というか、職種や立場関係なく、全員が「お客様に対して真摯に向き合うこと」を大事にしているからだと思います。
私が取り組んでいる「ダイバーシティ&インクルージョン (vminclusion)」も、社内でそういう仕事があるわけではなくて、気持ちのある人が自発的に集まって進めています。私も、ただ楽しいから通常業務との兼務でやっているだけ。こうした活動を通しても、横のつながりが生まれやすい環境だと思います。
縛られない働き方だからこそ成果につながる
━━ヴイエムウェアはずいぶん前からリモートワークの制度を取り入れていたとか。
はい、以前からその制度はありましたが、明文化されておらず曖昧でした。実際、「周りの目が気になる」などの理由で取り入れにくいという声が多くて。そこで、リモートワークが可能であることをはっきりさせようと、3年ほど前に、“どこで仕事をしても良い”という制度「work@anywhere」をつくりました。
そもそも私たち自身がデジタルワークスペースを商材として提供していますから、それをまずは社内で積極的に活用してリモートワークが可能であることを体現していくということでもあります。
社員は皆、自分で予定を決められて、自分のスケジュールをオープンにしています。例えば、保育園に迎えにいく時間は仕事を離れる、お客様先に行く時には近くのカフェで仕事をする、などという働き方も当たり前のように取り入れています。効率良く働ければ場所はどこでもいいし、それで成果が上がれば最高ですから。
私も3年前に軽井沢に引っ越して、週に何日かは家で仕事をしています(取材時はフルリモートワーク)。そうすることで、新幹線に乗っている往復4時間分が自分の時間になるので、朝は近所に写真を撮りに散歩に出かけたり、一緒に暮らしている犬達とドッグランに行ったりして、毎日を楽しんでいます。

━━オンオフがつけられて良いですね。自由な環境で働くことで、より生産性が高まっていると。
そうだと思います。新型コロナウイルスの影響で、今年はずっとリモートワークが続いていますが、それぞれが自分のスケジュールをきちんと共有して、自分で時間の使い方や仕事の仕方を決めるという働き方自体は以前から変わっていません。
無駄にダラダラ仕事をすることもなく、すごく効率的ですよ。ミーティングもできる限り短時間にして、とにかく効率重視でどんどん進めます。こういうところは、良い意味で外資らしいところかもしれませんね。
でもそれでいて、何かトラブルがあった時は、遅い時間だろうと皆で集まって、解決するまで真剣に話し合い、強いチームワークで乗り切る。
だから、マネージャーとしても「みんなちゃんとやっているかな?」と心配したり、予定表を見ていちいち確認したりする必要がありません。逆に、効率が上がりすぎて仕事ばかりしている人がいるので、「ちゃんと休みなね」と声をかけるくらいですから(笑)

「腹落ちするまで会話する」が小林流のマネージメント
━━マネージャーとメンバーとの間の信頼関係も構築されているんですね。
先ほど、働く場所や時間が自由だという話をしましたが、「仕事のやり方」も同じだと思っていて。これはマネージャーとしてメンバーに仕事をどう任せるか、という話でもあります。
できるだけ枠を広げて、それぞれが自由にアイデアを出せる環境をつくることがポイントだと思うんです。仕事の目標が明確で、且つそのためのアプローチを自由に考えられる状態であれば、人はどこでも働けると思うので。これがメンバーへの信頼にもつながるのではないかと。

━━小林さん自身がマネージャーとして意識していることはありますか?
人って「腹落ち」しないと、やらないと思うんです。だから「納得してない」と思ったら、とことん話します。みんなが納得して腹落ちした状態になってから進めるようにしているんです。そうでないと力も出ませんし、特に今は在宅勤務で人の目もありませんから、やらされているという感覚で仕事をしていたら、なかなか進まないですよね(笑)
━━なるほど。意志を持って仕事に取り組みたい人にとって、とても良い環境ですね。
はい、こういうカルチャーの会社ですから、逆に人から何か仕事を与えられて、それだけをこなせばいいという考え方の人にとっては、ものすごく居心地が悪いかもしれません。社内にはどんどん意見を出して積極的にやりたいという人が多く、そういう人にとっては働きやすい会社です。
とはいえ、チーム力があるので、サポートできる体制はしっかり整っています。自走できないからほったらかしにされるということもありません。外資系企業の良い部分と日本的な良さを兼ね備えた、暖かみのある職場だと思っています。
- TEXT BY 志村江
- PHOTOS BY 吉田和生
- EDIT BY 谷瑞世(BNL)