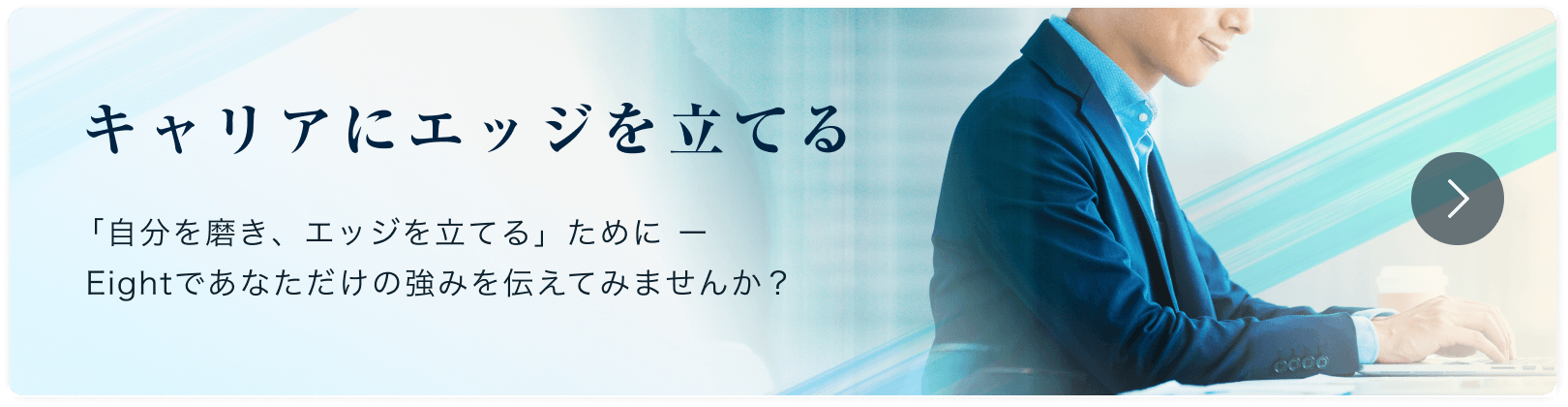※この企業の求人は現在掲載されていません
国境なき医師団には、医療に直接携わらないメンバーもいることを知っているだろうか。医師や看護師の世界中で医療活動を行うためには、インフラを整え、活動しやすい環境をつくる非医療従事者の活躍が欠かせない。もともとは会社員だった人も多いという非医療従事者の活動、そして働くということに対する意識の変化について聞いた。
ロジスティシャンの役目は、医療と財務以外のすべてを行うこと
2019年7月、松田隆行は南スーダンのジュバ国際空港に降り立った。蒸し暑い。気温30度を超えるが、7月は雨季にあたり、これでも涼しいほうだ。
「国境なき医師団」のベストを着けたスタッフが出迎えにきていた。ランドクルーザーに乗り、首都ジュバの町なかにある拠点に向かう。高層ビルはないものの、道路は舗装されている。
国境なき医師団は、紛争や自然災害などで緊急に医療を必要とする人々のために活動する団体だ。1971年にフランスで設立された。現在は世界38カ所に事務局がある。
松田は、国境なき医師団が南スーダンで展開しているプロジェクトの「ロジスティシャン」として赴任した。松田にとって初めての活動だ。
ロジスティクスは物流管理という意味で使われることが多いが、国境なき医師団のロジスティシャンが担う業務はもう少し幅広い。
「どんな仕事をしているのと聞かれるといつも困ってしまうのですが(笑)。大きく言うと、『医療と財務以外のすべて』をやるのがロジスティシャンです」

松田は、国境なき医師団に参加する前に、JICA(独立行政法人国際協力機構)の海外協力隊に参加した経験がある。専門学校を出たあと、自動車整備士として国内メーカーのディーラーに入社。9年目にJICAのプロジェクトに応募した。
「もともと人道支援に興味があったんです。かっこいいなという憧れと、海外で働きたいという気持ちもあって。パプアニューギニアの職業訓練校で2年間、自動車整備科の講師をしました」
任期を終えると元の職場に復帰した。しかし数カ月経つと、何かが違うと感じるようになった。
「パプアニューギニアに行っているあいだに(自分と日本での環境とのあいだに)感覚的なずれが生じていたんだと思います。理想を追い求めたい、また人道支援の現場で仕事がしたいという気持ちが募りました」

紛争地や被災地の「最前線」へ
しかし、人道支援や国際協力をする団体は他にもある。なぜ国境なき医師団だったのだろうか。
「『医療に国境はない』というコンセプトがしっくりきたのと、最前線まで行ける団体なんですね。他の団体だと退避勧告が出ているような場所には行けないことが多いので」
「最前線」とは、実際に紛争や災害が起きている場所を指す。それは遠い国の話ばかりではない。日本でも、東日本大震災発生直後、国境なき医師団は津波の傷跡も生々しい地域に入り、仮設の診療所を立ち上げた。
東日本大震災の被災地でのプロジェクトは、活動の一部を地元の社会福祉協議会などに引き継ぎ、比較的短期間でクローズされた。日本では、国や自治体が中心となって被災者支援が行われることが多い。
一方、政情が不安定な国ではそうはいかない。特に紛争地では、根本的に紛争が解決されない限り、どんなに傷口をふさいでも、また戦闘が起きて血が流れる。南スーダンはそんな国の一つだ。約半世紀におよぶ内戦の末、2011年にスーダンから独立したあとも、政府軍と反政府勢力の戦闘や、部族間の衝突が繰り返されている。
国境なき医師団は、独立前から南スーダンで活動を続けてきた。現在は現地採用を含む3500人以上のスタッフが活動している。各地につくられた病院には、銃撃にあって手や足を吹き飛ばされた男性がかつぎこまれ、栄養失調でやせ細った子どもを抱いた女性が訪ねてくる。妊娠合併症に苦しむ妊婦や、未熟児で生まれてくる赤ちゃんも多い。
松田は、そんな「緊急医療の最前線」で働くことを選んだのだった。といっても、いきなり前線に放り込まれるわけではない。最初の4カ月は、ベースキャンプとも言うべき首都チームで働いた。
「首都にいるあいだの主な業務は、プロジェクトのサポートです。物資の調達や在庫管理、インターネットのトラブルなんかもありました。現場のスタッフから衛星電話がかかってきて『通信がないから調べておいて』とか」

その後、前線の一つである北部の町、オールド・ファンガクへ飛んだ。首都とプロジェクトの現場のいちばんの違いは「病院があるかないか」だという。
「現場に行くと、患者さんがいますから。私たちロジスティシャンは医療行為を行うわけではないので、患者さんとのかかわりは間接的ですが、それでも患者さんがいるのといないのとでは仕事の中身が全然違いました」
オールド・ファンガクの周辺は湿地帯だ。患者にはマラリアやコレラなどの感染症が多い。川をわたり沼地を歩いてようやく病院にたどりついたときには重症化しているケースもある。人の移動にも物資の輸送にも車両が不可欠だが、悪路のためしばしばトラブルが発生する。
「私は(自動車整備士の)専門職ではなく、ジェネラルのロジスティシャンですが、一通り自動車のことがわかるのは役に立ちました。あとは電気系統ですね。首都以外の場所では、住居や病院に発電機を使っているところが多いんです。最近の自動車には電気の知識が欠かせないので、電気系統のトラブルも図面を見ながら不具合を探すことができます」

その他にも、ワクチンや医薬品の在庫は適正か、次はいつ何を送ってもらうかを常に管理しておかなくてはならない。建物が壊れれば修繕するし、清潔な水も必要だ。スタッフが生活するための衣食住も整えなくてはならない。あらゆることがままならないへき地で、医師や看護師、薬剤師らが医療活動を行うための一切を、数人のロジスティシャンが下支えする。
「やることが多すぎて自分でも気付かないうちに限界に近づいていたりするんですけど、そういうときは必ずリーダーが『大丈夫?』って声をかけてくれるんですよ。『それを考えるのはいったんやめて、こっちに集中しよう』とか。なんでわかったんだろうと思うぐらい絶妙なタイミングで、的確な指示をくれました」
無理強いはしない。最優先はいつでも個人
今年3月末、松田は9カ月の活動を終えて帰国した。次は北アフリカのリビアに行くことが決まっている。
「はじめて行ってみて、もうちょっとやりたいし、できるようになりたいという気持ちが強かったので、リビア派遣のオファーを受けました」
国境なき医師団の仕事の特徴の一つは、どんな場合でも断ることができるということだ。派遣される前もそうだし、現場でもことあるごとに意思を確認される。
たとえば、3月にWHOが新型コロナウイルス感染症のパンデミックを宣言したとき、松田は南スーダンにいた。
「3月半ばに『帰りたい人は遠慮なく手を挙げてください』という案内がありました。帰ったスタッフもいましたし、残ったスタッフもいました。私はもともと4月5日までの契約で、たまたま後任が着任したので、予定より1週間早く切り上げて帰国しました」
「個人を最優先に考えてくれるのは、この団体の大きな魅力の一つですよね」
そうあいづちを打つのは、ロジスティシャンとして12回の派遣経験をもつ吉田由希子だ。
「紛争地でも、もし本人が『怖い、これ以上は精神的に無理だ』と思えば、無理強いはされません。すごく大切にしてもらえている感覚があります」

吉田がはじめて国境なき医師団の活動に参加したのは2012年。最初の派遣先は、松田と同じ南スーダンだった。
吉田が「当時のジュバは、首都といってもルーラルエリア(=へき地、この場合は医療活動が展開されている場所)みたいな感じで、空港にもなんにもなくて」と言うと、松田が「いまは変わったんですよ」と笑う。
吉田の最初の活動は、内戦で傷ついた人々にワクチンを届けるプロジェクトだった。「エマージェンシーミッション」と呼ばれる緊急支援で、いきなり現場に放り込まれた。
「でもワクチン接種キャンペーンにはロジスティシャンが多数参加するので、ベテランさんもたくさんいるんです。わからなかったらなんでも聞けるので、安心できました」

以前にザンビアやインドで人道支援活動に参加したことがあり、アフリカでの生活も経験済みだったが、紛争地ははじめてだった。
「南スーダンでは複数回活動をしていて、銃声が聞こえこともありました。でも意外と、予想していたような怖さは感じませんでした」
独立したとはいえ、国境紛争や部族間衝突が頻発していた時期だ。なぜそれほど怖いと思わずに済んだのだろうか。
「チームが一緒にいるからだと思います。地元のスタッフやベネフィシャリー(=受益者、この場合は患者さんたち)も含めて、一緒にいるということが怖さを軽減してくれました。それに、ロジスティシャンはチームを守る側なんですよね。プロジェクト・コーディネーターと一緒に避難計画を立てたりなど、安全管理を担う立場だということも大きかったと思います」
技術面も精神面も。あらゆる人がメンターになる
吉田はその後、イラクやトルコ、シエラレオネなどで活動を重ねた。派遣期間は数カ月から9カ月。イラクに次いで長かったヨルダンでは、シリア難民向けの診療所の立ち上げに参加。最初の1カ月で1100人の患者が受診した。
「何もないところに診療所をつくるわけですから、全部自分たちでやらないといけないんです。チームは多国籍ですから、日本の常識は常識ではないんです。そんななかで自分を最大限に生かしていくことを考える。それは、自分を知ることでもあるんですね」

自分の限界はどこにあるのか、バーンアウトしないためにはどうすればいいか。自己管理能力が磨かれていった。「それでもやっぱり日本人なので、寝る間を惜しんで働いてしまうんですけどね」と笑う。迷ったり悩んだりしたときはどうするんですかと聞くと、「相談できる人がたくさんいるので」とあっさりとした答えが返ってきた。
「首都にいるロジスティック・コーディネーターは、同じポジション経験者なので気持ちもわかってもらえることが多いんです。技術的なサポートのみならず、精神面でも支えてくれる」
隣で松田がうなずく。国境なき医師団の活動の現場では、ある意味で、あらゆる人がメンターなのだった。松田はこんな話をしてくれた。
「あるとき、ロジスティックチームの同僚と世間話をしていたんですね。同じ年ぐらいだったかな。彼は南スーダンの人で、休みに地元に帰ると言うので、何気なく『家族に会うの?』と聞いたら、『家族は全員いなくなった』と言われて。内戦で家族も親戚もみんな亡くなったし、その現場も見てるって。ふとしたときにそういう話を聞くと、やっぱり感じるものがあります。普段は本当に、ふつうに同僚なので」
「そういうの見せないですよね」と吉田が言う。
「すごく強いなって、学ぶことが多いです。南スーダンは特に、国内避難民が地元スタッフとして採用されているケースが多いんですね。つらい思いをしているスタッフが少しでも希望をもてるようなかかわりができたらなという思いでは、いつも接しているんですけどね……」

国境なき医師団は、キャリアの選択肢のひとつになり得る
松田も吉田も人道支援に対する熱い思いを持っている。同時に、その思いを身勝手に相手にぶつけないように、ものすごくコントロールしている。人道支援における、まさにプロフェッショナルの態度だ。
一方で、吉田は「国境なき医師団での活動を『仕事』と呼ぶことに抵抗がある」と言う。
「いろんな国の同僚と話して感じたことですが、活動に参加している一人一人が、できる限りのことをしたいという思いで集まっているという感覚があるんです。やりたくなくてやっている人は一人もいないと思います。だから『仕事』よりも『活動』と言うようにしているんです」
とはいえ、思いだけでは続けられない。給与が支払われるのは派遣されているあいだだけだ。生活の不安はないのだろうか。
「私の場合は、特にアルバイトもしませんでした。向こうでは生活費も多少支給されそんなにお金を使わないので、お給料が口座にたまっていくんです。次の派遣までの数カ月は、そのお金で十分生活できました。それに、毎日出勤するんやったら、女の子は洋服もお化粧品もいると思いますけど、向こうに行ったら泥まみれ(笑)。活動に参加しはじめてから、どんどん物欲がなくなっていきました」
松田も同様で、会社勤めのころよりも収入は減ったが「別に困ったことはない」と事もなげに言う。

松田も吉田も、自分たちが特別だとは少しも思っていない。ただ一つ言えるとしたら、自分が変わっていくことを恐れない人たちだ。
「お金では買えないものがたくさんあるんです。それが得られる団体だと、私は思っています。経験を通じて視野が広がるし、価値観も変わります。私は、自分がやりたいことを人生の軸におけるようになりました」(吉田)
「会社員をしていたときは、必要以上に将来のことを気にしすぎていた気がします。もちろん将来も大事なんですけど、老後のために生きているわけではないし、いまを大事にしないとと思うようになりました」(松田)
吉田は2年前から、国境なき医師団の活動から離れている。活動だけが人生ではないし、家族のなかにも果たすべき役割がある。戻りたいと思うときがきたら、人事の担当者に相談するつもりだ。そうやって相談できる人がいることが、この団体の魅力でもある。
これまで一緒に働いた人のなかには、「夏休みだから来た」という人や、還暦をすぎてから活動に参加しはじめた人もいたという。
「日本でも、いまの若い方は終身雇用や年功序列といった働き方からは遠ざかっていますよね。国境なき医師団で活動することが、多様な選択肢の一つであってくれたらいいなと思います」

- TEXT BY 長瀬千雅
- PHOTOS BY 吉田和夫
- EDIT BY 谷 瑞世