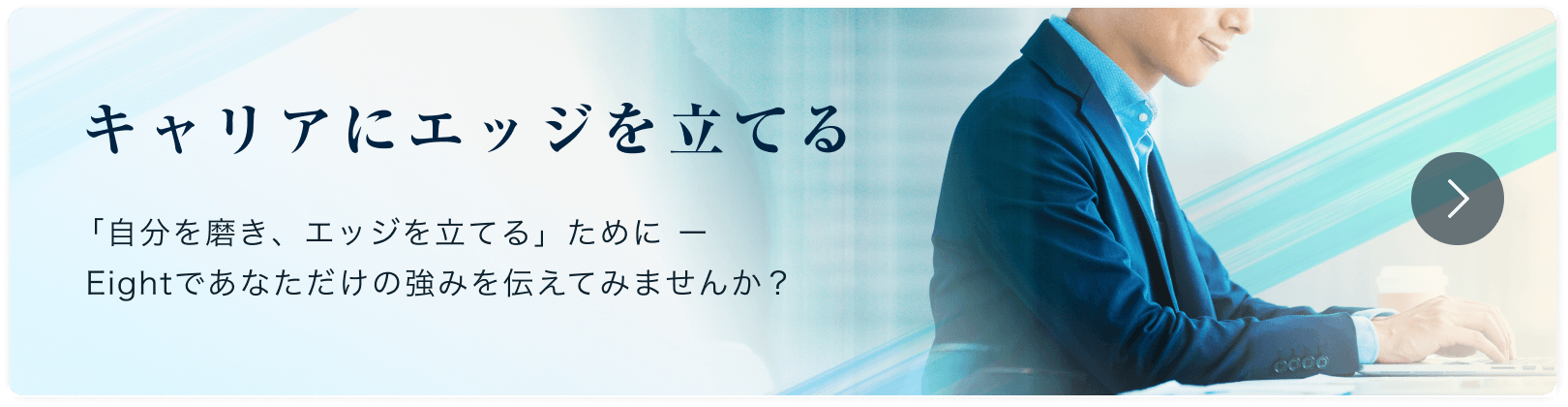※この企業の求人は現在掲載されていません
デザインを経営の資産と捉えて活用することで、ブランド構築とイノベーションを推進していく「デザイン経営」。企業の存在価値を改めて定義し、目指す姿を実現していく手法としても注目されている。こうした経営手法は、キーワードだけが先行してしまい、その実体が伴わないケースも少なくない。
では実際に企業において、どのようにデザインの価値を浸透させ、活用させていくべきものなのか?本特集『経営にデザインをかけ算する』では、デザインを経営資源として重要視する企業へのインタビューを通して、その実践と組織変革について紐解いていく。
これまで主に広告やコミュニケーション、商品企画などの分野で扱われてきた「デザイン」を経営の資産と捉え、活用していく「デザイン経営」が注目されている。しかし一方で、「経営」と「デザイン」をいかに掛け合わせていけばいいのか、具体的なイメージを掴めずに戸惑っているビジネスパーソンも少なくない。
そうした中、株式会社LIFULL(以下、ライフル)では2017年より、国内外のクリエイティブアワードを受賞してきたデザイナーの川嵜鋼平を執行役員CCO(チーフ・クリエイティブ・オフィサー)に迎え、デザイン経営を積極的に推進している。
実際の企業内において、どのようにデザインの価値を浸透させ、いかに活用すればいいのか。そして、経営におけるデザインの効果は、どのようなものなのか。同社のデザイン経営推進の中心人物である、川嵜に話をうかがった。
デザインが重視されない組織をいかに変えるか
――川嵜さんが入社された当時、LIFULLの社内における「デザイン」の扱いは、どのようなものだったのでしょう?
4年前のことですね。当時はまだデザインという言葉の定義すら、まだちゃんとされていない状態でした。デザイナーも「制作」と呼ばれていました。もともと不動産・住宅情報のポータルサイトで創業し、開発力や営業力で成長してきた会社なので、クリエイティブに積極的に投資していくという考え自体、あまりない印象を受けました。

2017年LIFULL入社。執行役員Chief Creative Officerとして、ブランド戦略、ブランドデザイン、プロダクトデザイン、マーケティング、新規事業、研究開発など、グループ全体のクリエイティブを統括。またクリエイティブ組織の立ち上げから行い、戦略策定・育成・採用など、組織づくりも担う。それ以前は、J. Walter Thompson Japan、beacon communications k.k.に所属し、Nike、Nestle、P&G等の企業のクリエイティブディレクションを数多く手がける。Cannes Lions金賞、One Show金賞、CLIO金賞、Spikes Asia グランプリ、ADFESTグランプリ、文化庁メディア芸術祭優秀賞をはじめ、国内外の180以上のデザイン・広告賞を受賞。
――では、川嵜さんに声がかかったのは、そうした状況をなんとか変えようと?
弊社代表の井上高志から声がかかったのですが、当初から「デザイン力の強化」を課題として話していました。井上自身、会社をより成長させていくためには、企業としてクリエイティビティを高めていくことが不可欠だと考えていたようです。
私は最初、デザイン領域の責任者として入社しました。しかし、会社としての競争力を高めていくには、中長期的な視点でブランド構築もしていかなければならない。そして、ブランド構築するためには、その指針となるビジョンやパーパスをしっかり定め浸透させていかなければならない。そういった経緯で、デザイン以外の領域にもCCOとして管掌するようになったんです。
――決してデザインフレンドリーな組織とは言えないところから改革に着手されたわけですが、まず何から始められたのでしょう?
まずはデザイナーという職種の定義を変えていきました。私が入社する前は、みなさん「Webデザイナー」と呼ばれていて、Webサイトのデザインに関わることが主な仕事という認識でした。
そういった状況から、デザイナーには社内の各等級、各職階でどのような専門性が求められるのか、スキルマップとして可視化し、人事制度に反映していきました。目指したのは、発想力・表現力・実行力をそなえたデザイナーです。
表面のビジュアルだけではなく、事業戦略やブランド戦略を理解しコンセプトから考えられる発想力。UI/UXデザインやグラフィックデザインなども含めた幅広いデザインを扱える表現力。スケジュールとクオリティなどを担保できる実行力。そういった広義のデザイン力を持った人材の育成です。
――しかし、それは個々の社員にとって、今までの働き方からの大幅な変更も意味しているはずです。必ずしもすんなりと受け入れられたわけではないと思うのですが、どのように意識を変えていったのでしょう?
やはり、「何のためにこれが必要なのか」を丁寧に話していったことでしょうか。弊社はビジョンをとても大切にしている会社です。我々はこういうビジョンを実現したい。だから、デザイナーにはこういう専門性が求められる。というように、あくまで会社のビジョンを基点に話をしていくことが重要だったと思います。
さらに、こういった方針をデザイナーに腹落ちしてもらうため、「LIFULL DESIGN SCHOOL」という社内向けのスクールも開講しました。
そこではサービスデザインだけでなく、グラフィックデザイン、フィルムプランニング、コピーライティングやフォトディレクションまで、デザインにまつわるさまざまな講義を行っているのですが、どれも足下の業務と紐付いた講座内容にすることで、自分たちのやっていることが、ちゃんと日々の仕事につながっているんだと実感してもらう。そういった教育プログラムも行うことで、デザインマインドを浸透させていきました。
基本的にはデザイナーを対象にしているのですが、講義内容が好評で、今ではサービス企画、マーケターやエンジニアなど、さまざまな部署の社員が参加するようになっています。
社内の意識改革に近道はない
――デザイナー以外の方もスクールに参加されているというお話がありましたが、デザイン経営を推進するためには、非デザイナーの社員にもデザインへの理解を促していかなければなりません。そのための工夫や取り組みも行っているのでしょうか?
その意味では、全社を巻き込んだ「コンパ」というイベントが役立っていると思います。それはひとつのテーマを社員がディスカッションする場で、以前からよく行われていました。その中でブランド定義に関するワークショップをしたり、「LIFULL アジェンダ」というLIFULLが実現したい未来のために解決すべき社会課題をテーマに議論したりと、経営理念やビジョンに関するテーマも扱うことで、会社が目指す方向性への理解と浸透を推進しています。
ほかにも、役員のWebコラムの中で、ブランド定義の意図やプロセスを動画コンテンツとして複数回に分けて配信したり、「LIFULL FONT FAMILY」という社内で制作したオリジナルフォントを配布する際に、制作チームが込めた意図を解説する動画を配信したりと、意識的にクリエイティブに触れてもらう機会を設けています。

――非デザイナー、非クリエイティブ職の社員にとって、こうした教育の機会は直接業務に結びつくわけではないことから、「どうして自分が学ばなければならないのか」という反発を招くことがあります。そこをLIFULLでは、いかに乗り越えていったのでしょう?
これには秘訣はなく、とにかく一貫性を持ってやり続けるしかないと思います。一般論として、今の多くの日本企業が抱えている課題とは、短期的な収益ばかりを追い求めた結果、しっかりとしたブランド構築ができていないことに起因するものだと感じています。これを変えるには、ひたすらブレずにブランディングをし続けるしかない。それしかないと思いますね。
判断基準となる「ルール」をあらかじめ作る
――川嵜さんがおっしゃったように、短期的な収益ばかりを追い求めたら、一貫性のあるブランド構築は難しいと思います。その一方、経営層から、デザイナーやクリエイターから見てブランド価値を毀損しかねない取り組みを、収益が見込めるからと求められることもある。このジレンマには、いかに対処すべきでしょうか?
それも基本的には、会社の経営理念に立ち返って判断するべきことだと思います。
例えば、弊社には「利他主義」という社是があります。そして、経営理念を実現するための行動規範としてのガイドラインがあり、さらに「LIFULL Quailty Standards」というアウトプットを出す際の品質基準もあります。我々は行動規範や品質基準といったものを経営陣やグループ会社含めて、全社横断で策定しているんですね。
そういったものがあれば、短期的には収益があがるかもしれない活動でも、本当に品質基準を満たしているのか、そもそもビジョンに合致したものなのか、客観的に判断して意思決定ができるようになります。
――ブランド価値を保つための判断基準になるルールを、経営層のレベルであらかじめ定めておくということですね。
そうですね。それも自分の重要な仕事のひとつです。弊社は代表の井上をはじめとした経営陣が、すごく経営理念やビジョンを大切にしているので、こういった仕組みづくりの重要さも理解されやすかったと思います。
――では反対に、現場はデザインやクリエイティブにもっと力を入れたほうがいいと思っていても、肝心の上司が理解してくれないといった場合は、どう説得していけばいいでしょうか?
それは結果で示すしかないと思います。私も現場にフルコミットしていたときは、とにかく結果を出して黙らせるということをしていました(笑)。あとは日々のコミュニケーションの質と量ですね。
例えば、今年の世界最大のクリエイティブアワード「カンヌライオンズ」でグランプリを受賞した作品がある。それについて上司に「どう思いますか?」と聞いてみる。「私はこう思うのですが」と。そうやって業務外の、かつ対外的に高く評価されているデザインやクリエイティブについて議論を交わすだけでも、互いが持っている価値観が交わると思います。
そうやって互いの好き嫌いを明らかにしていく中で、何を重視しているのかという人間性を互いに理解するし、上司にもクリエイティビティに興味を持ってもらう第一歩になる。だから、そういう日常的なコミュニケーションを積み重ねていくことから始めるといいのではないでしょうか。
クリエイティブアワードを狙った意外な理由
――川嵜さんがLIFULLのCCOに就任されてから4年が経ちました。現在、社内におけるデザインの重要性の認識は、どのくらい浸透してきたと感じていますか?
難しい質問ですね。毎年、毎クールごとにチャレンジばかりなので、自分の中では常に目標は未達という印象なのですが、組織としてはすごく成熟してきたと感じています。
当初こそ組織改編にともなってデザイナーの退職者も出ましたが、今はシニアデザイナーやアートディレクターがどんどん育ってきています。最初の頃は私がレイアウトや文字組みといったアウトプットの細かいところまでインプットしていたんですね。でも、今は提出されたものに対して大きな方針についてのディレクションやフィードバックするだけで大丈夫な状況になってきました。
――さまざまなインナー向けの取り組みの中で、特に効果的だったものは何でしょう?
先ほどの話にも関連しているのですが、外でしっかり結果を出したことかなと思います。
実はここまでお話した社内向けの取り組みや日々のミッションと並行して、自分でクリエイティブディレクションをする「地球料理 -Earth Cuisine-」というプロジェクトを立ち上げたんです。
間伐材を使った「Eatree Cake ~木から生まれたケーキ~」、放置竹林の竹と笹を使用した「Bamboo Galette -竹害から生まれたガレット-」など、「食べることが地球のためになる、地球の新たな食材を見つける」というコンセプトのもと、さまざまなシェフや生産者と共に商品開発をしてきました。
これはLIFULLがソーシャルエンタープライズとして「世界で最も多様性を認め、社会課題に向き合う企業」としてのブランド認知を獲得するために行ったものではあるのですが、もうひとつの実施理由がありました。それは国内外のクリエイティブアワードで、しっかり評価されるアウトプットを出そう、そうすることでインナーの意識を変えていこうという目的です。
実際、ニューヨークの「Art Directors Club」や「グッドデザイン賞」など40を超えるアワードを受賞したことにより、チームのメンバーが「何かすごいことをやっている」「あの人たちの話を聞いてみよう」と社内で思われるようになりました。メンバー自身も成長し覚醒したと思いますし、広義のデザインの重要性をもっとも認識してもらえた取り組みだったと思います。

ゴールは「LIFULLらしさ」を文化として作ること
――川嵜さん自身の仕事への向かい合い方も、一人のデザイナーだった時代とは変わってきた?
それはありますね。前は個人プレーでしたけど、今は自分が世の中に何かを出すのではなく、人を育成し、その人が成長して、チームとしてすごくいいアウトプットを出してくれる。そんなときに組織でものづくりをする醍醐味を感じるようになりました。
そして、組織でものづくりをしているからこそ、個人では達成できないインパクトを社会に与えることもできる。その面白さを日々実感しています。
――自分がどう評価されるか、から、人にどんな影響を与えることができるか、に興味が変わってきた、と。
例えば、ワイデン+ケネディというポートランド発の世界的に有名なクリエイティブ・エージェンシーがあります。広告代理店は人の出入りが激しい業界ですが、人が入れ替わっても、継続的に素晴らしいクリエイティブを生み出し続けているんですね。それはなぜかと考えるに、ワイデン+ケネディらしいカルチャーが社内にしっかりと根付いているからだと思います。
自分がLIFULLでやりたいことは、まさにこれです。彼らのように確固としたビジョンに基づいた企業カルチャーを作ることで、LIFULLを素晴らしいアウトプットを生み出し続けられるクリエイティブ組織に成長させていきたいですね。
――それはつまり、たとえ川嵜さんがいなくなっても、LIFULLらしいアウトプットが生まれる環境を作ることが、ご自身のCCOとしての役割ということですね。
まさにそのとおりです。そこが最終的な目標です。

- TEXT BY 小山田裕哉
- PHOTOS BY 小財美香子
- EDIT BY 瀬尾陽(Eight Career Design)