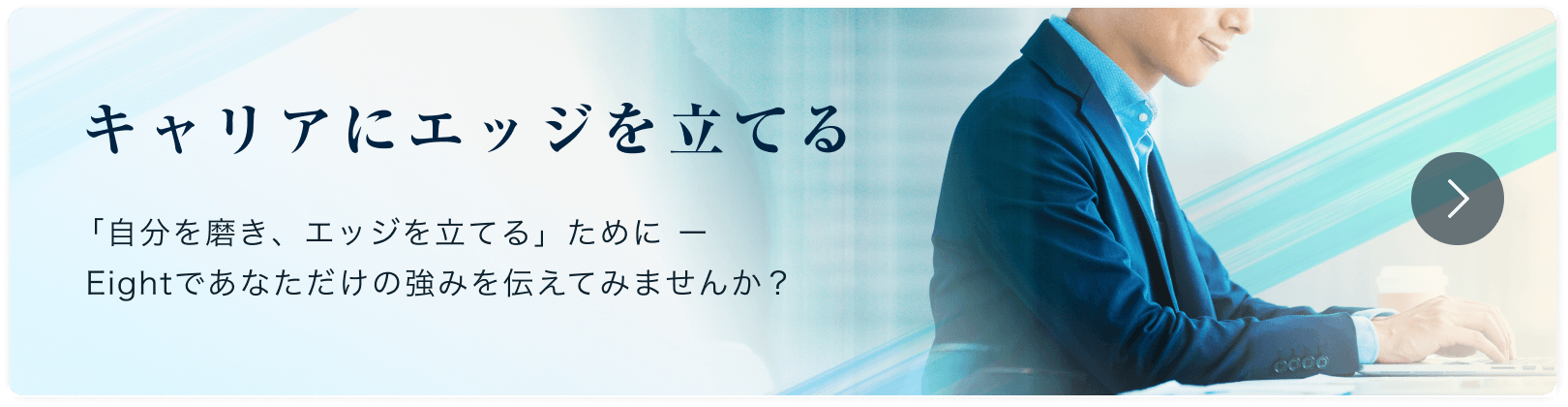※この企業の求人は現在掲載されていません
会社組織における「対話」の重要性が指摘されることが増えている。一緒に働く仲間同士が「わかりあう」ことなしにいい仕事はできないだろうということが、よく言われるようになった。
しかし、組織づくりと対話やナラティヴ(物語)の関係性にいち早く注目してきた経営学者の宇田川元一は、こうした「わかりあうためのものとしての対話」という論調に、「それでは組織はよくならない」として異を唱える。
グロービスもまた、組織改革の手法として対話的アプローチを重視する。「練り上げられた戦略が真に有効なものになるには、組織やその構成員一人ひとりが、戦略を実行できる状態へと変わる必要がある。この『人・組織が変わる』のに対話が非常に有効なのだ」とグロービスの西恵一郎は言う。
そこで今回は、宇田川と西の二人に、いま組織に真に必要な対話とはなにかをテーマに対談してもらった。「組織改革はむしろ、わかりあえないとわかることから始まる」と語る両者。ぼくらは対話に関して、どんな誤解をしてしまっているのだろうか。
対話とは、改革の思想である
西:我々の仕事はクライアント企業のいわゆる組織開発のお手伝いをすることですが、企業によって組織のあり方は一つひとつ異なるし、組織の構成員も一人ひとり違う。なおかつ常に変化しています。だから、ぼくは普段から「組織は生き物だ」と思うようにしているんです。経営者の人たちは、そうした生き物のような組織をとある方向へと成長させたいと思っている。そのサポートをするのがぼくらの役割です。
具体的には、「個人の能力を伸ばすこと」と「ベクトルを一つの方向に向けていくこと」の二つのお手伝いをするのですが、この後者に「対話」がすごく大事になるというのが、私の認識です。というのも、「やらなければならない」というコミュニケーションは、放っておいても上から降りてくる。けれども、多くの人はそれに納得しない状態で動いています。だからパワーが出ない。「やらなければならない」ではなく、その人自身が「やりたい」状態をどうにかしてつくる必要があります。「対話」はそのための有効な手段だと捉えています。
宇田川:ということは、西さんのお仕事はトップも含めての改革ということになるわけですね。それは私が考えていることと非常に近いと感じました。最近の私の知的関心は、まさに改革に向いています。私が言っている「対話」とは「改革の思想」なんです。よく言われるような「わかりあうためのもの」ではない。わかりあえなさがある中でどう改革していくか、変革していくか、という話です。
となると、変わらなければならないのは組織を構成するメンバーの側だけではない。そのように働きかける側もまた変わらなければならない。双方が変わることによって初めて、やれることも変わっていくわけです。ですから、西さんのお仕事は便宜上、「経営トップが新しい戦略・方向性をつくるプロセス」と「できたものを組織に浸透させ、メンバーがコミットできる状態をつくるプロセス」の二つに分けられると思うんですが、その両方が対話的である必要があります。

埼玉大学経済経営系大学院准教授。2000年立教大学経済学部卒業。02年同大学大学院経済学研究科博士前期課程修了。06年明治大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得。 06年早稲田大学アジア太平洋研究センター助手、07年長崎大学経済学部講師、准教授、10年西南学院大学商学部准教授を経て、16年より埼玉大学大学院人文社会科学研究科(通称:経済経営系大学院)准教授。 専門は、経営戦略論、組織論。 ナラティヴ・アプローチに基づいた経営変革、戦略開発を中心に研究を行っている。また、様々な企業のアドバイザー、メンターとして、その実践を支援している。 2007年度経営学史学会賞(論文部門奨励賞)受賞。19年、著書『他者と働く━━「わかりあえなさ」から始める組織論』を出版。
西:ええ。そうですね。
宇田川:前者の例としては、マイクロソフトのCEOサティア・ナデラが、同社と自身の関係が再構築されていった過程を描いた『ヒット・リフレッシュ』という本がおもしろい。彼のお子さんは奥さんのお腹の中にいる時に窒息して脳に障害を持って生まれてくる。それで人工呼吸器につながれるのですが、その人工呼吸器が自社のOSで動いていることを知り、ナデラは自分たちのプロダクトにどんな価値があるのかを改めて実感したそうです。
一方で彼自身はエンジニアだから、技術の動向をいろいろと知る中でクラウドの重要性が見えてきたという話、あるいはアップルなどとの競争に負けていく痛みや、セクショナリズムが進んでどんどん不愉快な会社になっていくのを変えたい思いなども描かれる。この本では、そういうさまざまな状況に取り組む中で新たな戦略・方向性が見えてきたということが語られている。私が前者の意味で言う対話的なプロセスとは、まさにこのようなものです。
西:トップが発する戦略の背景や、トップ自身の価値観や思いをメンバーに伝える必要があるということですね。
宇田川:はい。後者に関しては、よく「巻き込む」という言い方をしますが、これは物事の片面しか見ていない。一方ではトップ自身が「巻き込まれる」必要もあります。そうでなければ、メンバーにとって意味のある言葉として語ることはできないからです。「巻き込む」「巻き込まれる」の二者が不可分になって初めて対話的と言えるんです。トップがつくった方針をただメンバーに向けて発信して……というのは、対話ではない。
だから、先ほど便宜上二つに分けさせてもらいましたが、実はこの二つはくっついているんです。これまでの過程でメンバーがどんな痛みを抱えていて、どういう苦しみがあり、でもどういう可能性を感じていて、そこにはどんな市場があるのか。さらには、トップ自身はどう感じていたのか。そうしたさまざまなナラティヴの接点をつくっていくことが対話です。一見するとトップがメンバーを巻き込んでいるように見えるけれども、同時にさまざまなナラティヴにトップ自身が巻き込まれ、参入していなければ、両者に橋はかかりません。
ロジックを包むナラティヴが共感を生む
西:我々としてもそうやって橋をかけなければ組織は動かないと思ってやっているのですが、クライアント企業の経営層とお話をしていると、その優先順位は決して高くない印象です。経営者はコミュニケーションを疎かにしたいとは思ってはいないものの、実際には社員の「自主性」という言葉のもとに、「方針は出した。あとは理解して実行していくのが社員の役割だ」というコミュニケーションになっていることも多い。ここに日本企業の一つの課題があると感じます。
宇田川:論理思考力が高い”優秀な人”からすると「こちらは正しい論理に基づいて方針を打ち出しているのだから、現場はそれに従いさえすればよい」という意識があるのでしょう。そういう人の論理自体が間違っているとは思いません。思わないが、実践的ではない。どれだけ正論を言ったところで効果を生まなければ意味はないわけです。リーダーがメンバーを動かし、本当に理想的な状態をつくっていくためには、自分から見て正しいというロジックだけではダメ。メンバーみんなが登場人物になっていけるような物語がなくては、そのロジック自体が機能せず、結果的に人は動きません。
西:おっしゃる通り、我々も最終的には組織のメンバーみんなが物語の登場人物になっている状態を目指すんです。けれども、いきなりそこにはいけない。まずやらなければならないのは、リーダー自身が自分の言葉で物語を語れるようになることだと思っています。
日本企業の多くのリーダーは自分の言葉で語ることが苦手です。企業がどうしたいか、組織がどうなったらいいかというロジックは語れても、そこにその人らしさのようなものが出てこない。だから、ぼくらが大企業の人と向き合う際にはまず「あなたはどうしたいのか?」と聞くことから始めます。社会と会社と組織と個人という四つのレイヤーがあるとすると、それらが線でつながって初めて物語は生まれます。まずはリーダー自身が自分の言葉で語れるように働きかけ、その上でいかに共感をつくるかをお手伝いするというのが、我々のやっていることです。

株式会社グロービス グロービス ・コーポレート・エデュケーション部門マネジング・ディレクター 。三菱商事株式会社にて、不動産証券化、コンビニエンスストアの物流網構築、商業施設開発のプロジェクトマネジメント業務に従事。B2C向けのサービス企業を立ち上げ共同責任者として会社を運営。グロービスの企業研修部門にて組織開発、人材育成を担当し、大手外資企業のグローバルセールスメソッドの浸透、消費財企業のグローバル展開に向けた組織開発他、多くの組織変革に従事。海外法人を立上げ、現地法人の経営を行う。現在はコーポレート・エデュケーション部門マネジング・ディレクター兼中国法人の董事を務める。
宇田川:「自分の言葉で語れない」というのは、要は自分が述べていることが、実は他人事になっているということですよね。それなのに、メンバーに対してだけ「他人事のように仕事をするな」と言うのは、欺瞞でしかない。
組織がうまくいかないことの背景には、おっしゃるような経営者自身の違和感を覚えた出来事はもちろん、社員や顧客の反応など、さまざまなことが「点」として存在しているはずです。組織としてよい実践をするためには、自分の中の正しいロジックは一旦置いておいて、なぜうまくいかないのかを「観察」し、こうした「点」を集める必要があります。それらを結ぶことで初めて、背後にある物語が像を結び、なにが起きているのかが見えてくるのです。
医療には、「ナラティヴ・メディスン=物語医療」と呼ばれる領域があります。医師や看護師が患者をケアする際には、患者が「よくわからないこと」を言ってくる。それが科学的に見れば意味のないことや間違っていることだとしても、患者は患者としてなにかを物語ろうとしている。つまり、医療者と患者との間にはナラティヴの溝がある状態です。これを医療者側の正論で切り捨ててしまうのは、よい医療とは言えません。特に、慢性疾患の場合は顕著で、医療者だけでは問題が解決できません。慢性的に続く病気は、患者自身にも参加してもらわないといけないし、場合によっては患者の家族の参加も必要だからです。
こう考えると、専門知識はありながらも、それだけではよい医療を行うことができない慢性疾患ケアの専門家と、経営戦略や大局的な視座からの論理はありつつも、一人の力ではどうすることもできない経営者というのは、近いものがある。ここで大切なのは、正論を振りかざさず、起きていること、特におかしいなと思うことをよくよく観察してみて、それが一体相手のどんなナラティヴにおいて合理性があるのかを探っていこうとすることです。

組織はリーダーを映す鏡である
西:リーダーがメンバー一人ひとりの背後にある「点」を読み解けなくなっているのには、働く従業員の価値観の変化が大きいと感じます。ぼくらの10個上の世代の時代は当たり前のように体育会系の世界で組織が運用されていました。40歳過ぎのぼくらはギリギリそれがわかる世代ですが、30代前半ともなると、もはやまったく理解できない。そこにギャップがあります。
ギリギリわかる世代の多くは自分が教えられたのと同じように、体育会系のやり方で下と接しようとします。そこに悪気は一切ない。良かれと思ってやっているんです。けれども、価値観のまったく異なる若者からすれば、それはすごく押しつけ感があるし、フィットしない。だからパフォーマンスも上がらない。この、押しつけている側に押しつけている自覚がないことが大きな問題なんです。自覚がないままだと相手について理解しようとはならない。だからいつまで経っても解決しない。
宇田川:おっしゃる通り、世代間ギャップはバカにならない問題ですよね。世代のナラティヴというものがどうしてもあるから。ただ、いくら読みづらいとは言っても、「観察」していれば違和感くらいはあるはずで。その違和感に気づけないのはリーダー自身に「準備」ができていないからだと思う。
その「準備」とはすなわち、「自分自身が問題の一部なのだ」と自覚することです。マネジメントで言うなら、「人が育たないのは自分のせいでもある」と気づくこと。それをせずに、ただ教えられたように教え、育てようとすると、相手は動かない。それで「部下が育たない」とただ嘆き、自分でカバーしようとしてプレーイングマネジャー化していく。するとどんどん忙しくなって、部下がどんな思い、どんな考えでやっているのかを見る余裕はますますなくなっていく。でも、最初のところで「自分にとって困ったことが起きているのは、自分が部下のことを理解できていないからではないか」というところにちょっとでも目が向くと、そこからやりようが見えてきます。
西:我々がリーダーと接する際にしているのも、まずは「知らず知らずのうちにそういう状態になってしまっているよ」と伝えること、そして「組織はリーダーを映す鏡である」と伝えることなんです。部長や課長の人たちはよく「うちの組織はあまり挨拶をしないんです」「雰囲気がちょっと暗いんです」とおっしゃる。でも、それはあなたが挨拶をしないからだろう、と。リーダー自身が挨拶せずに仏頂面で座っていれば、それは組織も暗くなりますよ。結局、組織で起きていることはリーダー自身の行動の結果です。ここに向き合って自分を変えていけば、組織も変わっていくことになる。

宇田川:ただし、自分一人ではこの自覚は難しいですよね。そのために必要なのも対話だし、まさに西さんのように、外から働きかける存在なのだと思います。ぼくはよく「孤独はいいが孤立はダメだ」と言うんですが、その際に例に出すのが、映画『ボヘミアン・ラプソディ』。あれはフレディ・マーキュリーの孤独との戦いを描いた作品です。なぜ孤独はいいのかと言えば、孤独とはその人のオリジナリティだからです。ほかの人と違う道を選ぶから孤独になる。天才であるゆえんとも言えます。けれども、あの映画でもよく描かれていたけれど、孤立はダメ。孤立すると、自分一人でぐるぐると考えて、どんどん変な方向に行ってしまう。ダイアローグではなく、モノローグになってしまうから。
「わかりあう」とは、「わかりあえない」とわかること
西:もう一つお話ししたかったのは、組織と組織の関係です。経営者の方は組織と組織を結びつけることで「シナジー」を生もうとするのですが、ぼくは「シナジーはファンタジー」だと思っていて。
そう思う理由は二つあります。一つは構成員の意識。別の組織にいる人のことは「所詮、自分たちとは違う人たちなんだ」と分ける意識が生まれやすい。そのせいで、組織同士の仲が悪いということが、どの会社でも起こっています。そのままでは当然、シナジーなど生まれようがありません。もう一つは、組織によってKPI、つまりは背負っている目標が違うこと。組織はどうしたって目標に対して最適化されますから、KPIが違う組織がシナジーを生み出そうと思っても、それは無理なんです。その無理なところに橋をかけるのもぼくらの役割なのですが、この点に関して、宇田川さんはどう思われますか?
宇田川:ぼくは大学では経営戦略論を教えているのですが、アンゾフ・マトリックスを使って経営統合によるシナジー効果の説明をする際には、ぼくも裏話として「シナジー効果なんて疑わしい」という話をよくします。その時に例に挙げるのが、ダイムラー・クライスラーの合併の失敗です。例としては少し古いですが、この合併は、教科書的にはシナジーが大発揮されるはずでした。ダイムラーは北米の販売網が弱いし、クライスラーはヨーロッパの販売網が弱いから、お互いの弱点を補完できる。次世代の自動車開発で共通の研究開発投資ができるし、部品の共通化もできる。ところが、実際に蓋を開けてみたら、高級車と大衆車では部品のクオリティに差がありすぎるなど、いろいろと問題があって、額面通りにはいかなかったんです。
けれども考えてみれば、同じことは様々な企業のグループ化がうまくいったフォルクスワーゲングループにも当てはまるわけです。ということは、大事なことは「一見してありそうだったシナジーが思ったほどなかった」という話の先にあるのではないか。理屈の上であるとなっていたシナジーがなかった時になにをするのか。ダイムラー・クライスラーはそこに失敗していたのではないかと思うのです。
西:ああ、なるほど。買収前に分かるに越したことはないですが、難しい時もある。大切なのは、シナジーが効かないと分かってから、どのように戦略をアジャストして、そして組織が戦略に呼応して新しい価値を創れるかですね。
宇田川:対投資家向けのロジックとして「戦略的にはこうだ」と言うこと自体はいいんです。ですが、マネジメントというのは本来、それをどうリアライズするかに本当に大事なところがあるはずです。お互いに全然違うカルチャー・価値観で車を造ってきた2社だし、KPIも当然違う。大事にしたいものも違う。という中でどうすればいいのかと言えば、「合併したのだから、理屈の上ではこういうふうに協力して、こういうものを造らなければならない」という綺麗事を言うのは一回やめて、お互いなにが違うのか、その違いと向き合ってみる。その上で、「少なくともこういうことをやっていったら、なにか価値がつくれるのではないか」と、現実に即して考えていくことだったのかもしれません。

西:我々がお手伝いしているクライアントの中には、シナジーを生み出すことに成功している企業もあります。積極的に買収し、背景も事業領域も異なるいろいろな会社がグループに入ってくるにも関わらず、シナジーを生み出せている。なぜかと言えば、その企業には理念があり、そこにストーリーがあるから。その考え方・価値観に対してはみんなが共感するから、やっていることは違っても「そこでつながっていればいいよね」という状態が出来上がっている。だからシナジーが生まれるのではないか、と。
宇田川:それは逆説的に言うなら、お互いの違いをちゃんと見られる状態にするために、ある一点においては同意していこうということなのだろうと思います。「違うけど、ここは仲良くしよう」「ここを基盤にしよう」ということなので。「なんで話が通じないんだろう」みたいな時に、「違うのはしょうがないよね。その上で、じゃあどうしようか」となることが大事なのだと思う。自分が事前に思っていた理屈が通用しなかったというのは、たしかにその時はショックだけれど、でも、それはもっとやりようがあることを告げてもいると思うのです。ぼくは平田オリザさんの『わかりあえないことから』という本がすごく好きなんです。日本人はお互いを同じだと思っているから対話が起きない。逆に「おんなじじゃないけど、それでも一緒になにかを生み出していこう」となった時に対話は生まれるし、それぞれがもっている差異が価値になり、リソースになる。
西:それこそがダイバーシティの本質的な部分ですよね。その違いをどう経営に活かすのかを意識して対話をつくらなければ、ダイバーシティも意味がない。正論を言うだけで対話をしない人は、目的が「多様性をつくること」になっていて、「多様性を活かして成果を出すこと」ではなくなっています。
宇田川:ぼくの本を読んだ後輩の研究者が「これは大人になる本だ」と言ってくれたのですが、言い得て妙だなと思いました。自分にとって不都合なこと……例えばいまだって新型コロナウイルスで、どうすることもできないことがたくさん起きているけれど、「そんな状況でもやれることはなにか」と考え、やっていくのが大人じゃないですか。「わかってほしい」と思う気持ち自体はわかるんです。でも、「じゃあ自分は向こうのことをどれだけわかっているのか」という話もあるわけで。わかっていないのはお互いさま。だから、非常にトリッキーな言い方ではありますが、「わかりあえないことがわかる」というのが、対話の中核に据えられているものなのではないでしょうか。

- TEXT BY 鈴木陸夫
- PHOTOS BY 西田香織
- EDIT BY 谷瑞世(Eight Career Design)