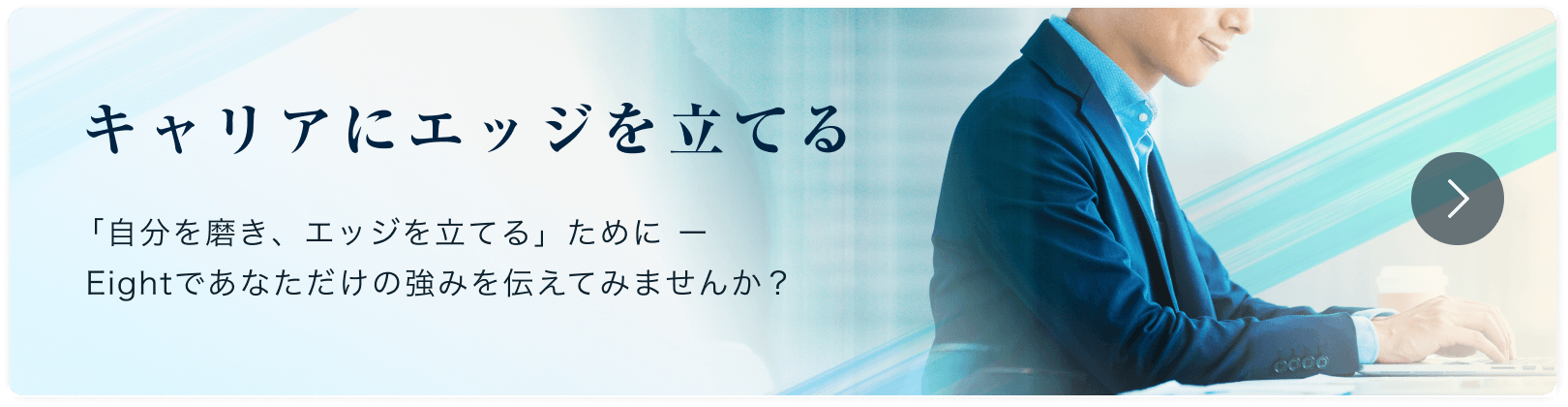※この企業の求人は現在掲載されていません
グロービスの法人部門で多くの経営者を外部パートナーという立場から支えてきた西恵一郎は、「日本企業が不振に陥る原因の多くは戦略の欠如にあるのではなく、せっかく作った優れた戦略が人・組織のケイパビリティに合っていないことにある」と指摘した。この説に立つなら、日本企業が再生するにはまず人・組織の側が変わる必要があることになる。
ところが、日本企業の人事は多くの場合「人・組織の専門家」として経営を支える役割を必ずしも担いきれてはおらず、自分たちの力だけで組織を変えるのは難しい。だからこそ、長期にわたって伴走し、人・組織が変わる手助けをする外部パートナー・HRBPの存在が重要になる。グロービスの法人部門は、まさにそうした仕事に携わっているという話だった。
では、人・組織は実際にどうやって変えていけばいいのか。今回は2018年度に企画・発足したセガサミーグループの企業内大学「SEGA SAMMY College」の立ち上げプロジェクトを例に、彼らの仕事を見ていこう。
ゲーム大手のセガとパチンコ・パチスロ機器の開発・製造を行うサミーが2004年に経営統合し、設立されたセガサミーホールディングス。グループの事業は、サミーを中心とする遊技機事業、デジタルゲーム分野を中心にアミューズメント機器・施設、アニメーション、トイなどを提供するエンタテインメントコンテンツ事業、そして複合リゾート施設の運営などを行うリゾート事業から成る。
三つの事業はそれぞれ順調に成長している。一方で、組織文化も事業領域も、人事制度さえも異なるグループ全社が同じベクトルを向いて歩みを進めることは、非常に難しい。同グループは 「感動体験を創造し続ける」をグループミッションに掲げ、グループシナジーを創出し、世界の一歩先を行くエンタテインメント企業グループとして、確固たるポジショニングの確立を目指している。
そのためには、いまより一層グループ全社が一枚岩となり、事業シナジーを出していくことが不可欠であった。戦略をグループ全体として実行していくために、まさに人・組織が変わらなければならない局面を迎えていたのだ。
そこで浮上したのが、グループ企業間でバラバラだった育成の方針や制度を整理し、グループ横断で「セガサミーグループらしい革新者(リーダー)」を育成していくために、ゼロから企業内大学を立ち上げるという今回のプロジェクト。担当したのは、グロービスに入社して1年目、当時32歳の若手社員 大谷 康人だった。
人・組織を変える上で彼らが大切にしていることとはなにか。なぜそれが彼に実行可能だったのか。現場で奮闘する若手コンサルタントの言葉から、答えが見えてきた。
※この企業の求人は現在掲載されていません
グロービスの法人部門で多くの経営者を外部パートナーという立場から支えてきた西恵一郎は、「日本企業が不振に陥る原因の多くは戦略の欠如にあるのではなく、せっかく作った優れた戦略が人・組織のケイパビリティに合っていないことにある」と指摘した。この説に立つなら、日本企業が再生するにはまず人・組織の側が変わる必要があることになる。
ところが、日本企業の人事は多くの場合「人・組織の専門家」として経営を支える役割を必ずしも担いきれてはおらず、自分たちの力だけで組織を変えるのは難しい。だからこそ、長期にわたって伴走し、人・組織が変わる手助けをする外部パートナー・HRBPの存在が重要になる。グロービスの法人部門は、まさにそうした仕事に携わっているという話だった。
では、人・組織は実際にどうやって変えていけばいいのか。今回は2018年度に企画・発足したセガサミーグループの企業内大学「SEGA SAMMY College」の立ち上げプロジェクトを例に、彼らの仕事を見ていこう。
ゲーム大手のセガとパチンコ・パチスロ機器の開発・製造を行うサミーが2004年に経営統合し、設立されたセガサミーホールディングス。グループの事業は、サミーを中心とする遊技機事業、デジタルゲーム分野を中心にアミューズメント機器・施設、アニメーション、トイなどを提供するエンタテインメントコンテンツ事業、そして複合リゾート施設の運営などを行うリゾート事業から成る。
三つの事業はそれぞれ順調に成長している。一方で、組織文化も事業領域も、人事制度さえも異なるグループ全社が同じベクトルを向いて歩みを進めることは、非常に難しい。同グループは 「感動体験を創造し続ける」をグループミッションに掲げ、グループシナジーを創出し、世界の一歩先を行くエンタテインメント企業グループとして、確固たるポジショニングの確立を目指している。
そのためには、いまより一層グループ全社が一枚岩となり、事業シナジーを出していくことが不可欠であった。戦略をグループ全体として実行していくために、まさに人・組織が変わらなければならない局面を迎えていたのだ。
そこで浮上したのが、グループ企業間でバラバラだった育成の方針や制度を整理し、グループ横断で「セガサミーグループらしい革新者(リーダー)」を育成していくために、ゼロから企業内大学を立ち上げるという今回のプロジェクト。担当したのは、グロービスに入社して1年目、当時32歳の若手社員 大谷 康人だった。
人・組織を変える上で彼らが大切にしていることとはなにか。なぜそれが彼に実行可能だったのか。現場で奮闘する若手コンサルタントの言葉から、答えが見えてきた。
トップ同士の信頼関係から生まれた経営層向けプログラム
入社1年目でグロービスでの実績も経験も少なかった大谷が今回、従業員数7000名を超える企業の育成体系刷新という巨大プロジェクトを手掛けることになったのには、もちろん前段がある。
サミーの創業者で現会長の里見治氏はいまなお経営の最前線にいるが、会長の経営哲学の継承は、重要な課題でもあった。そこで現社長の里見治紀氏が、かねてより交流があったグロービス代表・堀義人に相談。一代で総合エンタテインメント企業を築き上げた会長のリーダーシップを次世代に継承すべく、2016年に社内経営塾「里見塾」を立ち上げた。このプロジェクトはトップ同士の信頼関係がベースとなり始まった。
里見塾とはひとことで言えば、グループ各社の経営層と里見会長の「対話」の場だ。里見会長がこれまでに行ってきた意思決定事例を鑑(かがみ)に、経営リーダーとしての判断軸や価値観、経営視点について考察を加えながら、経営者としてのリーダーシップのなんたるかを紐解いていく。グロービスはその全体設計から事前のコミュニケーション、当日のファシリテーションまでのすべてを同グループの社長室と二人三脚で担ってきた。
大谷は里見塾がスタートして2年目の2017年に入社。すぐに運営メンバーの一人としてアサインされた。そこで対面したのは、エンタテインメント業界の荒波に打ち勝ってきた経営陣ばかり。「最初は正直、気後れもしました。一方で、参加するみなさんは、私の言うことになんの先入観も持たずに真摯に耳を傾けてくれて。それがすごくうれしかったのと同時に、最後まで伴走して、参加者の方の成長にコミットする覚悟が決まった感じがします。」
今回の企業内大学「SEGA SAMMY College」の立ち上げプロジェクトは、この「里見塾」の考え方がベースになっている。組織が一枚岩になるには経営陣のみならず、社員一人ひとりが「あるべき姿」を共有している状態が望ましい。そこで、それまで各社それぞれで運用されていた育成体系とは全く異なる、グループ横断での新たな人財育成の計画が立ち上がった。そして、里見塾を通して「あるべき姿」に触れていた大谷が、プロジェクトの運営だけでなく、設計から携わることになった。
「経営者同士の信頼関係があるからこそ、教育プログラムの表面的な話ではなく、本音で話せる深い議論になる。グロービスでのキャリアが浅い自分がその重要な案件を任され、貴重な経験ができる。それはすごくストレッチな成長につながるし、自分が成長していければ、ゆくゆくはそうした機会を後輩に提供する側にも回ることができると思います」
その過程では当然、現時点のスキルや知見だけでは対応できない事態も度々発生するが、社内のコミュニケーションツールでひとたび質問や相談を投じれば、ものの1時間で経験豊富な講師や社内の研究機関、先輩コンサルタントからの山ほどのリプライがつく。自分の知見を惜しみなくシェアする文化があり、こうしたサイクルがうまく回っているのは、グロービスで働くことの大きな魅力ではないか、と大谷は言う。

「あるべき姿」の具体化を妥協しない
企業内大学を設計するにあたり、大谷が行ったことは「①あるべき人財要件・行動指針の策定」「②あるべき姿を起点とした育成体系の創出」「③育成施策・カリキュラムの設計」「④グループ展開・運用の設計」の四つのステップに集約できる。平たく言えば、まずは最終的に目指す「あるべき姿」を定め、一方で現状を把握し、そのギャップを埋めるべく具体的な施策を考えていくということだ。
プロジェクトはスタートから約半年で方向性を定め、ローンチに向けて決裁を取るというタイトなスケジュールで進められたが、大谷はその半分近くの時間を「①あるべき人財要件・行動指針の策定」に費やしていたという。
「目指す頂が定まっていなければ、いくら手段の話をしても仕方がない。すべてこれを起点に考えることが重要だと考えたからです。今回で言えば、里見会長のリーダーシップを鑑にするという大きな方向性だけは事前に決まっていましたから、里見会長のリーダーシップとは具体的になにを指すのかを徹底して言語化することから始めました」
まずは里見塾で語られた内容をベースに、里見会長のリーダーシップを「5つの力」としてまとめた(正確に言えば、里見塾を通じて言語化された里見会長の人間力をまとめた社内書籍を一つの指標とした)。次に、各役職階層に求められる期待要件を「5つの力」に照らし合わせて一つひとつ言語化。さらに、それを経営力・人間力と分類し、コンピテンシーレベルにまで落とし込んでいった。
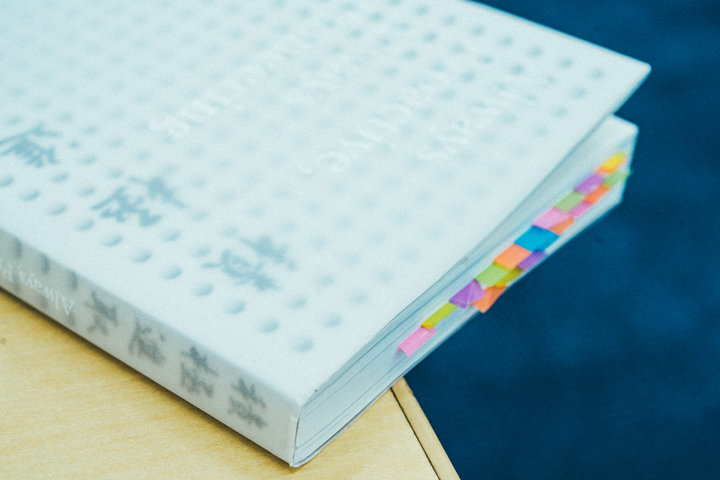
「目標や夢って抽象的になりやすいし、曖昧模糊としているじゃないですか。ここがゆるゆるだと、なにをやっても機能しないんです。特に研修や育成などの人を動かしていく場では、そういうことが起こりやすい。抽象的なものを具体的に言葉にしていくのは、地味ですが極めて大事な営みだと思っています」
西も強調していたが、「言語化」は彼らの仕事の根幹をなすキーワードの一つだ。それを外部パートナーという立場から行うのには二つの意義があると大谷は言う。一つは、外部の客観的な視点を入れることで、定めた目標が自己満足で終わるのを防ぐこと。もう一つは、常に「あるべき姿」に立脚し続けられることだという。
「私の勝手な解釈ですが、セガサミーの担当部門の方は社内の事情や要望・声と、時に共存し、時に戦いながら変革を推進しています。現場から寄せられるさまざまな要望をさばく中で、目の前の現実や実行に引っ張られざるを得ないシーンも往々にしてあると思うのです。けれども、そうやって現実に引っ張られすぎて理想が見えなくなってしまっては、そもそもやる意味がなくなってしまう。現実と折り合いをつけるのはもちろん大切なことですが、一方で我々が外部パートナーという立場から、理想へと揺り戻す役割を果たすことも重要だと考えています」
設計図から「共創」する
人や組織を変えるにはまず「あるべき姿」を定め、具体的な言葉として形にすることがもっとも重要というのが彼らの考え方。だが、世の中の全てのプロジェクトが、設計の段階から深く関われるものとは限らない。
「多くのプロジェクトは、顧客からこういう提案をしてくださいという要件があらかじめ決まった状態で相談が始まります。それでいいものが作れるのか、それで本当に楽しいのかということには長らく疑問を感じていました。このことは、自分がグロービスに転職した大きな理由の一つでもあります」
例えば家を建てるとき、設計図が正しくなかったらいい家が建たないように、組織課題も押さえるべきイシューが間違っていたら、現場でどれだけ努力しても根本的な解決には結びつかない。そういう歯がゆさを感じながら仕事をしている人は、コンサルタント以外にも多くいるのではないだろうか。今回のケースが違うのは、そもそもなにを、どこまで目指すのかというところから議論が始まっていること。「最初に定めた『あるべき姿』をそのまま形に落とせたことが今回の価値ではないか」と大谷は言う。
なおかつ、それをセガサミー内部の担当者と共に考えられたところに、成功の大きな要因がある。大谷は「あるべき姿」を定めるまでの3カ月間、社長室の担当者と日々メールや電話でやりとりを重ね、また週に1回は対面でも対話を重ねて、アイデアをブラッシュアップさせていった。それは受発注の関係というより、目的を共にする共創の関係と言えた。
「先方自身の思いや覚悟が大変強かった。外部パートナー任せにせず、共に創り上げるという姿勢を示してくださったことにも感謝しています。一方でこちらとしても、もはやお金をいただいているからやる、という感じではなくて。お互いに最高にいいものを作るためにはなんでもやろうという理想的な関係が築けました。その分、日々正解のない議論や、互いの意見や考えをぶつけ合うようなやりとりが続いて、大変ではありましたが」
新しい育成プログラムはすでに運用が始まっているが、クライアントからは「これで完成ではなく、継続的に一緒にブラッシュアップしていければ」と言われているという。「研修や育成は効果検証しにくい分野ではありますが、そのための仕組みを作ることが今後のチャレンジになるのではないかと思っています」
ある意味で”納品”のない共創関係が、継続的なビジネスチャンスを、そして大谷自身の成長の機会をももたらしている。
「運用」まで責任を持ってこそ
「あるべき姿」を描くことに多くの時間と労力を割くことができた。内部の担当者と二人三脚で行うことができた。そのことが大谷に大きな手応えをもたらしているのは確かだ。だが、今回のプロジェクトを振り返って、もっとも「しんどかった」のはこうした「設計図を描く」プロセスではなかった。
「本当にしんどかったのは、むしろできたものを全社に広めていく段階でした。『自社の従来の育成との整合性や棲み分けはどうしたらいいのか』とか『もっと早いサイクルで施策を回すべき』とか、現場からたくさんの意見があがって。でも、考えてみればそれは当然なんです。各社、それだけ本気で取り組んでいるし、期待していますから。要は、実際に運用する段階で発生する壁があるということに、自分が思い至らなかったという話。そのせいで担当者の方が苦しんでいるのを見るのは、とてもつらい経験でした」

このプロジェクトの期間中にはもう一つ、こんな出来事にも遭遇した。
「前職時代に採用の面接・選考設計をお手伝いしたクライアントの方と偶然再会して、何気なく『あのプロジェクトはその後どうなりましたか?』と尋ねたら、『現場に浸透させるのに時間がかかり、結局1年寝かせたんだよね』と。自分がいいと思って作ったものが現場に伝わり切らなかったこともショックでしたが、運用されないのにはそれだけの理由があるはずで。当時の自分が運用の段階で生まれる壁にまで目を向けられていなかったということのほうが情けなかった」
けれども、だからと言ってコンサルタントという仕事に絶望したわけではなかった。大谷にとってはむしろ、いままで以上にこの仕事にのめり込む動力にさえなっている。「今回のプロジェクトを通じてコンサルタントという仕事に対する考え方がガラッと変わった」と大谷は言う。
「設計図を描くのは言ってしまえば楽しい作業。でも、それを組織になじませ、実際に運用していくのにはまた別の壁がある。今回、そういう悩ましさを共有したことでハッとさせられたし、コンサルタントとしてできることがまだまだあるんだということを教えてもらいました。その可能性に気づかせてもらったという感謝の気持ちが強いです」