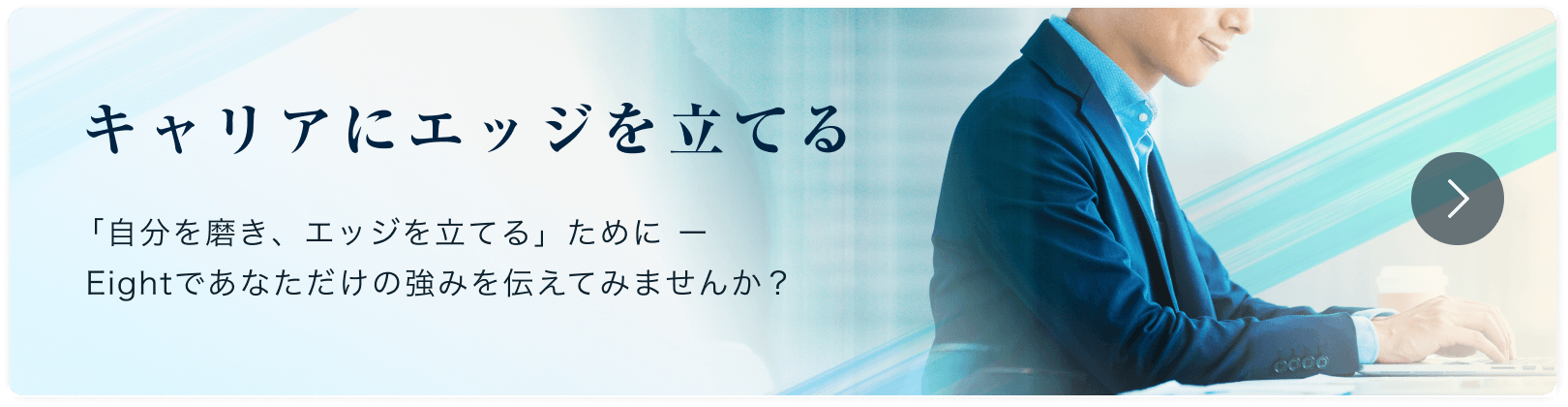組織改革には痛みが伴う──とは限らない。遊び心を持ち、日常とは違う実験的なモードで組織の新たな可能性を探っていく「プレイフル・アプローチ」という方法論がある。その可能性と実践法を、2020年6月に『問いのデザイン-創造的対話のファシリテーション』(学芸出版社)を上梓した、ミミクリデザインCEOの安斎勇樹に聞いた。
解凍、変革、再凍結──3つの組織変革プロセス
安斎が代表を務めるミミクリデザインは、商品開発や組織開発、人材育成、地域創生など幅広い領域でプロジェクトをファシリテートしている。最新の学術研究に裏打ちされたワークショップデザインの方法論を駆使した、日常を揺さぶる「問いのデザイン」によって、ボトムアップ型の学びと創発を引き起こすスタイルが特徴だ。2020年6月には、その方法論をまとめた『問いのデザイン-創造的対話のファシリテーション』を安斎と京都大学総合博物館准教授・塩瀬隆之の共著で上梓し、3万部を突破するベストセラーとなっている。
安斎がワークショップデザインに関心を抱くようになったのは、大学在学中、小・中学生向けの私塾を運営していたときだ。一方的な詰め込み型教育ではない「理想的な学びの場」を実現すべく、起業家やアーティストなどをゲスト講師に招き、体験型授業を開いていた。そこで出会ったひとりの少年の身に起きた変化が、安斎の原体験として印象に残っているという。
安斎勇樹(以下、安斎):その少年は毎月通ってくれていたのですが、吃音があって、アイスブレイクでもなかなかうまく話せなかった。でも、あるとき思いもよらぬかたちで、積極的に話せるようになったんです。きっかけは、他の子が知らない遊びを知っていたことでした。「えっ、何それ?」とみんなから注目を浴びてから、見違えるように喋れるようになった。「いったい何が起きているんだろう?」と衝撃を受けました。学習を強いるのではなく、自発的になって楽しく学んでもらう。それこそがワークショップの力なんだ、と。

その後、東京大学大学院学際情報学府に進学した安斎。博士課程に在籍中から、企業向けの事業開発や組織開発のためのワークショッププログラムに携わるようになり、ミミクリデザインを創業。今日に至るまで、ファシリテーションやコンサルティングを手がけてきた。その活動をベースに、企業や団体の「新商品のアイデアがなかなか生まれない」「社員のエンゲージメントを高めたい」「組織変革を推進したい」といった課題解決を支援するなかで、共通する問題点が浮かび上がってきた──それは現場を置き去りにしていること。
安斎:CIリニューアルや組織変革といったプロジェクトが立ち上がっても、経営層の一声で決まったがゆえに、現場の人は誰もやりたがっていないケースも少なくない。一人ひとりが自律性を発揮するボトムアップ型のアプローチでなければ、組織変革は成功しません。
そもそも、「組織変革」とは何を指すのか。安斎が参照するのは、アメリカの心理学者であり組織開発における源流の一人であるクルト・レヴィンが提唱した「3つの組織変革プロセス」だ。まずは、「解凍」。組織における文化や行動規範、価値観、ルーティンなどを溶かし、可変性を高めること。次に、「変革(移動)」。新たな目標設定や評価制度、あるいは組織構造やビジネスモデルに至るまで、必要に応じてあるべき姿に変化させること。そして、「再凍結」。変革によって生じた変化を定着させ、維持していくために、再び足場を固めることだ。
日常から離れ、内発的動機や衝動を解き放つ
企業や団体が組織変革に取り組む際、市場環境の変化や主力事業の停滞、従業員のエンゲージメントやモチベーションの低下などに対する「このままではマズい」という危機感から、トップダウンで意思決定がなされることが多い。むろん、経営戦略にまで至る変革をスピーディに成し遂げるには、強力なリーダーシップも必要だ。しかし、現場の課題感や葛藤に蓋をして、痛みを伴うかたちで組織変革を行う「ペインフル・アプローチ」は、ともすると多大な負担を強いることになる。
安斎:現場の声をないがしろにして、「こう言われたから」と思考停止したまま変革を実行すると、思うような成果が出なかったり、問題が起こったりする。だからこそ、内発的動機や衝動が解き放たれ、「ああしたい」「こうしたい」といった感情が燃えあがるような課題を設定し、日常から離れた対話のなかで組織変革の可能性を探る「プレイフル・アプローチ」が重要なのです。
プレイフル・アプローチによって組織変革に取り組んだ企業には、ある共通の変化が見られる。中間管理職などプロジェクトの実働チームを指揮するリーダーが、内発的な衝動のもと、突き動かされるように行動するスイッチが入るというのだ。プロジェクト始動前は「上司がこう言っている」「現場がどう思うかわからない」と、主語が“他人”だったのが、「僕らはこういうことをやりたい。上司と現場も説得しますから」と、主語が“自分”に変化するそうだ。

安斎:人材育成、組織開発、商品開発など、プロジェクトの目的はさまざまでも、僕らが指標にしているのは「クライアントがどれだけ変化したか」です。プレイフル・アプローチで“耕す”のは、内発的な衝動です。たとえば、トイレに行きたいと思ったら、勝手に行くのが自然です。トイレに行くのを我慢するのは滑稽ですし、いちいち許可を取るのもおかしな話。でも、実は多くの硬直化した組織で起こっているのは、こうした事象だと思うんです。従業員に能力が不足しているわけではない。本当はできるはずなのに、余計なルーティンや慣習を習得して、身動きが取れなくなっている。その「当たり前」を揺さぶり、アンラーン(学び直し)することで、ボトムアップの変革が起こるのです。
「プレイフル」という語感からは、LEGOブロックやボードゲームなどを使って行うワークショップのようなものをイメージするかもしれない。けれども、そうした「遊具」を用いるかどうかは、必ずしも本質ではないという。文化史家のヨハン・ホイジンガが『ホモ・ルーデンス』(中公文庫)で提唱したように、遊びは人間活動の本質であり、そこから文化が展開していくものである。人間の根源的な動機である遊び心やワクワクする気持ちをエネルギーに転換し、一人ひとりの自発的な行動を促すことが、プレイフル・アプローチの要諦なのだ。実践に際しては、「当たり前」とされる規範や価値観に揺さぶりをかける非日常的な場や条件を設定し、「普段とは異なるモノの見方を体験する」ことが重要だと安斎は話す。
安斎:人はどんなときに衝動を覚えて、「やってみたい」と思うのか。人間の普遍的な感情を理解して、探求しつづけることが重要です。でも、面白さを喚起するのは本当に難しくて、まだまだ研究の真っ只中。たとえば、「プレイフルに考えよう」とトップダウンに呼びかけたら、プレイフルじゃなくなってしまいますよね(笑)。
「つい解きたくなる問い」をデザインする
ワークショップにおいてプレイフル・アプローチを実践する際にカギとなるのが、「どんな問いや課題を投げかけるか」、すなわち「問いのデザイン」だ。ミミクリデザインが過去に手がけた、ある事例を紹介しよう。大手化粧品メーカーの資生堂が、2020年に向けて「TRUST 8」という行動指針を新たに策定した。「THINK BIG」「TAKE RISK」「HANDS ON」「COLLABORATE」「BE OPEN」「ACT WITH INTEGRITY」「BE ACCOUNTABLE」「APPLAUD SUCCESS」の8つだ。2018年当時、役職や職務、国籍も異なる世界中の資生堂グループ社員4万6千人に対し、その行動指針や組織ビジョンを浸透させるため、各部門・事業所単位でワークショッププログラムを実施することとなった。そこで投げかけた問いは、「もしこの8つの行動指針から一つ差し替えるとしたら?」というものだった。
安斎:「みんながつい解きたくなる問い」を設定することがポイントです。単に行動指針を唱和するだけでは、「やってみよう」とは思わない。でも、「行動指針が8つだと多いから、どれか消しちゃいません?」と投げかけると、現場の人たちは燃えるわけです。何かをぶち壊すとか消すとか、普段なら「ダメです」と言われていることを解き放ってあげると、衝動がくすぐられる。「どれにしよう?」「これは消しちゃダメでしょ」と対話していくことは、それぞれの行動指針を現場目線で再編集し、理解を深めることにつながります。
安斎が初めて企業向けのワークショッププログラムを手がけた、KDDI研究所(現・KDDI総合研究所)の事例も紹介してくれた。次世代技術の研究開発に取り組む研究員たちに対して、「つながらない携帯電話を考えよう」という問いを提示した。普段は「いかに通信の技術で人や情報のつながりを支援するか」という視点で物事を考えている者たちにとって、日常とは真逆の発想だ。
安斎:普段は嬉々として通信技術の話をしているタイプの人たちにこの問いを投げかけると、「えぇ!?」と頭を抱えるわけです(笑)。でも、つながらない電話にどんな価値があるかを考えると、「映画やドラマのネタバレを避けられる」「友達と直接会ってゆっくり話せる」といったかたちで、自然とユーザー目線で考えるようになる。普段とらわれている常識や立ち位置を認識して、それを揺さぶるような問いを投げると、発想が柔軟になるんです。
プレイフル・アプローチが機能する場面は、ワークショップだけではない。たとえば組織に何か問題が起こったとき、学習の機会と捉えるか、やり過ごすべきトラブルと捉えるかによって、プロセスは変わるだろう。
離職率の上昇、売上の低下……昨今のコロナ禍に伴う社会変化も、事象だけを捉えれば、いくらでもペインフルに解釈することができる。けれどもそこで事実を別の視点から解釈し、ポジティブにリフレーミングすることで、「問いの立て方」は変わってくるはずだ。
安斎は、ある示唆的なエピソードを紹介した。1975年、サンフランシスコ周辺の病院で、外科医たちによるストライキが一斉に起こったという。そのほとんどが対応できず、医療体制は危機的状況に陥った。だが、わずかながらその対応に成功した病院もあったという。その違いを分けたのは、ストライキという「起こった事象」に対する解釈だった。
安斎:多くの病院が「ストライキをいかに乗り越えるべきか」「いかにジレンマを克服すべきか」と考え、やり過ごそうとしていたなか、ある病院は「いまこそ革新的な医療サービスの可能性を探り、いろいろと試してみよう」と、その状況を受け入れた結果、すさまじい変革を遂げたのです。自分たちの足場が揺らぎはじめたとき、ピンチと捉えるか、学びのチャンスと捉えるか。その姿勢によって、大きく結果は変わってくるというわけです。
合理的なマネジャーが陥る“落とし穴”
ただし、プレイフル・アプローチの重要性を頭で理解していても、よほど意識しなければ、多くの人はペインフル・アプローチを取ってしまう。そこには、ある種の合理的な理由も存在すると安斎は指摘する。
安斎:ペインフルに捉えたほうが、組織のリソースを投下しやすいんです。明確な課題を設定したほうが合意形成しやすいし、見通しが良くなって確実性も高まる。誰が解決すべきかがハッキリして、説明責任も果たしやすくなります。合理的なマネジャーほど「誰が悪いのか」「誰がやるべきか」と状況を明瞭化しがちで、プレイフルに「曖昧な状況」を楽しむことができません。
課題として突きつけられているものだけを起点にアプローチし続けていると、思いもよらぬ新しい可能性は発見しづらい。固定観念に縛られ、“包丁を突きつけられた”状態よりも、日常から解き放たれ、「やってみたい」と自発的な状態で物事に向き合ったほうが、良いアイデアが生まれやすいのだ。

安斎:イギリスの詩人ジョン・キーツが提唱した「ネガティブ・ケイパビリティ」、すなわち不確実性や曖昧さのなか、その状態を受け入れ耐えられる力が、いま改めて注目されています。ネガティブ・ケイパビリティが求められているのは、そこからイノベーションが生まれる可能性があるからだと思います。不確実な状態を受け入れられてこそ、サクセストラップに陥り、新しいことに挑戦できない状態を回避できるんです。
皮肉にも、コロナ禍はあらゆる個人、あらゆる組織に不確実で予測不可能な現実を突きつけ、「当たり前を揺さぶる」機会となった。先行き不透明ないまだからこそ、不確実性や曖昧さに対して「プレイフル」に向き合い、柔軟に変化しつづける組織のあり方が、ますます求められていくだろう。
安斎:「不要不急の実験を平時からできる組織」が理想的なのではないかと考えています。環境変化に対して後手後手に対応するのではなく、不要不急の実験を繰り返して、はじめから「変わる」前提で状況を乗りこなしていく。それこそが「プレイフル」なのだと思います。実際、ミミクリデザインは、コロナ禍を経て成長した手応えがあります。もとから「両利きの経営」を志向し、探索と深化を繰り返していたからではないでしょうか。
コロナ禍では“遊び”の部分が真っ先に切り捨てられ、排除されてしまった。このウイルスの性質上、物理的な制約を避けられない側面はあるものの、「頭のなか」でどんなことを想像し、空想しても、それをとがめられることはなかったはずだ。思考すること、考え続けることには、終わりがない。そうしたプレイフルなアプローチを繰り返すことで、新たな突破口が開けるのだろう。
創造性とは「ものごとに飽きる力」
では、プレイフル・アプローチを実践していくうえで、組織のリーダーはどういった役割を果たすべきなのだろうか。
安斎:リーダー自身が、「プレイフル」の体現者であってほしい。「自分は変わらないしリスクも取らないけど、部下にばかりそれを求める」というのはおかしいじゃないですか(笑)。誰よりも日々の業務をプレイフルに楽しんでいるリーダーがいれば、「あ、そんなふうに試したり変えたりするのも許されるんだ」といった認識が広まり、組織は変わるはず。大げさな方法論は必要ありません。気分に応じて髪型や服装を変えたりするのと同じで、働いている一人ひとりの感情と向き合って、軽やかに変えることがあっていいと思うんです。
世にあるマネジメントの方法論や経営理論の多くは、いかに効率的に人を動かし、再現性高く事業を展開するか、あの手この手で思索を巡らせたものだ。そうしたフレームワークに対して、安斎は「プレイフル」に問いを投げかけ、インタビューを締めてくれた。
安斎:組織にとっては、仕組み化したほうが効率的かもしれないけれど、人ってそれだと飽きますよね? 詩人の谷川俊太郎さんが「あなたにとって創造性とは?」と問われたとき、「ものごとに飽きる力」だと答えたそうなんです。同じことを繰り返して、ルーティンに情熱を失ったとき、人には「飽きる」という感情が生まれる。だからこそ「遊ぶ」んです。制約をプレイフルに捉えて、「このアイテムを使わずにゲームをクリアしよう」と、遊びのルールを変える。「飽きる」ことを恐れず、素直な気持ちで、不要不急の実験を繰り返していくことが大切なのではないでしょうか。

- TEXT BY 大矢幸世
- PHOTOS BY 玉村敬太
- EDIT BY 小池真幸(モメンタム・ホース)